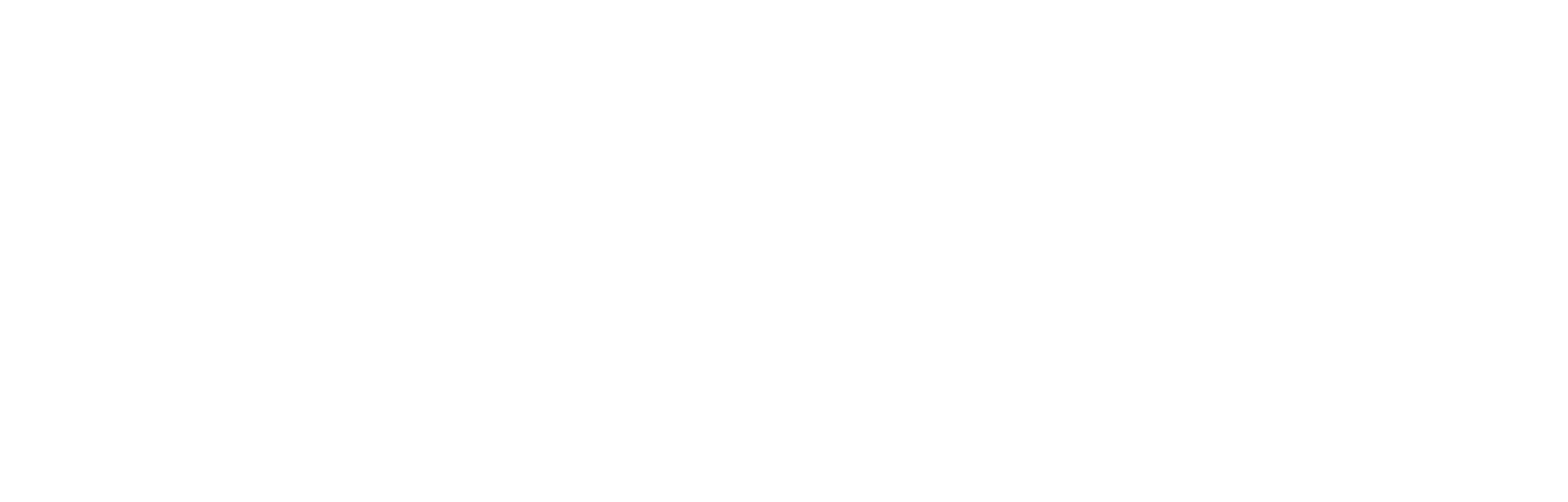
月別アーカイブ: 2025年5月
株式会社アルプス警備のよもやま話~第8回~
皆さんこんにちは!
株式会社アルプス警備、更新担当の富山です。
警備業務における行動規範と運用鉄則
― 現場判断の基盤としての原則と実践体系 ―
警備業はその特性上、異常事態の発生を“未然に防止する”ことに最大の価値を置く。
したがって、業務遂行においては属人的判断に依存するのではなく、明確かつ一貫した「行動原則(鉄則)」のもとで統制された実践が求められる。
本稿では、当社が警備実務において徹底している基本原則と、その背後にある業務倫理・判断基準について詳述する。
■ 1. 「何も起こらない状況」を構築する
警備における最良の結果は、**「事件・事故が発生しなかった状態を維持すること」**に他ならない。
これを実現するには、
-
現場環境の平常性の観察と記録
-
類型的リスクの先回り的把握
-
人流・物流・物理的障害物等の即時対応
等が日常的に実行されている必要がある。つまり、行動の結果より“兆候を察知する態度”の徹底が重視されるのである。
■ 2. 制服・態度・所作における第一印象の重要性
警備員は施設・現場における「顔」であり、訪問者・利用者・取引先に対する第一印象が、警備対象物に対する印象にも直結する。
-
制服の着崩れや不整備は、管理意識の欠如と見なされる
-
姿勢・挨拶・表情・立ち位置には統一感を持たせる
-
公私の区別を明確にし、施設内では終始緊張感を維持する
以上を徹底し、外形から信頼を醸成する姿勢を基本とする。
■ 3. 現場環境への“慣れ”を警戒する
同一現場における長期勤務は、状況の安定性を生むと同時に、リスク察知力の低下を招く恐れがある。
したがって、
-
毎日の巡回を「点検」ではなく「再確認」と捉える
-
常に“異常”の視点から現場を見る逆視的観察を心がける
このように「昨日と同じ」は現場における最大の錯覚であると認識することが重要である。
■ 4. 受容力のある対応姿勢
警備業務においては「管理する側」だけでなく、「相談される側」にも立たなければならない。
利用者・住民・通行人の訴えに対し、即答・断定せず、
-
傾聴
-
状況整理
-
適切な部署への引継ぎ
を迅速かつ丁寧に行うことで、現場の秩序維持だけでなく、警備員に対する対外的信頼性の向上にも資する。
■ 5. 判断よりも確認を優先せよ
緊急時において即断することは重要であるが、
不確定情報や曖昧な兆候に対して「独断」に走ることは、誤報・誤認・過剰反応を招きかねない。
-
連絡体制の即時構築
-
チーム内共有(インカム・帳票)
-
必要であれば映像・写真等の記録化
を実施し、状況を“確認の上で報告する”判断フローの堅持を優先する。
■ 6. 勤務終了後の整理整頓と報告の徹底
警備業務は「勤務時間中」だけで完結するものではなく、後工程を意識した情報共有と備品整備が極めて重要である。
-
日報記載内容の簡潔性と正確性
-
口頭・書面での引継事項の明確化
-
装備品(無線、ライト、手帳等)の点検完了
これにより、次のシフトが安全かつ円滑に運営される環境を確保することができる。
■ 結語:規律と自律による安全の実現
警備業務においては、偶発的トラブルへの対処能力と並び、日常のすべての行動に規律と自律が貫かれていることが何より重視される。
我々はこれらの原則を単なるマニュアルではなく、「組織文化」として日常業務に定着させることにより、
高度な信頼性と継続的な安全環境の維持を実現していくものである。
次回もぜひご覧ください。
![]()
株式会社アルプス警備のよもやま話~第7回~
皆さんこんにちは!
株式会社アルプス警備、更新担当の富山です。
警備の歴史的変遷と現代への接続
―人類史と共に歩んだ“守護”の制度とその発展―
警備という営為は、単なる労務や対処業務ではなく、社会秩序と公共安全の基盤を支える根本的な機能を担っている。
その成り立ちと変遷をたどることは、現在我々が従事する業務の本質的な意義と、社会的使命を再確認する契機となる。
以下においては、古代から現代に至るまでの警備に関する制度・職能の歴史的発展を概観し、今日の民間警備業の背景を明確にすることを目的とする。
■ 1. 原初社会における防衛機能の分化
狩猟採集生活における群れの存続には、外敵・猛獣・他集団からの襲撃に備える機能が必要不可欠であった。
これにより、自然発生的に「周囲を見張る者」や「夜間に警戒する者」が生まれ、共同体内での防衛担当の役割分化が進んでいったと考えられる。
この時点で、警備の原型は既に人類社会の中に萌芽していたといえる。
■ 2. 古代国家体制下の守衛制度と制度化
文明の成立とともに、都市国家や王朝が形成され、政治権力の集中に伴って制度的な守衛機能が確立される。
-
古代エジプト:ファラオの宮殿には「王室衛兵」がおかれ、神殿・財宝の警備も一任。
-
古代中国:秦〜漢代においては、「武官」と「警邏兵」が明確に区分され、都市部の治安維持が法令によって運用された。
-
古代ローマ:都市の防犯・消防を兼ねた「ヴィギレス隊」が存在し、現代の機動隊・消防隊の先駆けとなった。
日本では、律令制下に「左右兵衛府」「衛門府」などが設置され、天皇の近衛や宮中の秩序維持に従事。これが国家的警備機構の成立を意味する。
■ 3. 中世封建社会における自衛と番方体制
中世以降、中央権力の弱体化と各地の武士勢力の台頭により、治安維持は地域単位の自衛的対応へと移行する。
-
城郭や領主邸宅の「門番」や「番所番士」が、防衛および来客管理の任を負う。
-
鎌倉・室町期の武家政権では、軍事警察的な「侍所」や「検非違使」制度が活用された。
江戸時代に至り、幕藩体制が確立されると、都市部における常設的警備・巡邏体制が整備される。町奉行・与力・同心が中心となり、犯罪の予防・摘発が体系化された。
この時期の「火付盗賊改方」は、治安維持と警戒監視の機能を併せ持つ専門機関として、今日の警察機構と警備業務双方の先駆といえる。
■ 4. 明治維新と警察制度の近代化
明治維新以降、国家の近代化に伴い、欧米の制度に倣って国家警察制度が導入される。
1874年、内務省に警視庁が設置され、以後の治安業務は官の専権事項となっていく。
この時期、民間における警備業の役割は縮小したが、一方で私的な用心棒的存在や、工場等での独自警備体制が密かに形成された記録も存在する。
■ 5. 戦後〜現代における民間警備業の制度的発展
戦後日本において、経済の復興と都市化が進展するなか、**公的警察のみでは対処困難な“予防的・補完的治安活動”**の必要性が高まった。
1955年、日本初の民間警備会社が誕生。以降、ビル・工場・商業施設などにおける「常駐警備」「夜間巡回」「輸送警備」などが展開される。
1962年の「警備業法」制定を経て、業務内容は徐々に制度化・多様化され、今日に至る。
■ 6. 現代の警備業:人材と技術の融合体制へ
現在、警備業界は以下の複数分野に専門化している:
-
1号業務:施設警備(常駐警備、巡回警備、監視等)
-
2号業務:交通誘導・雑踏警備
-
3号業務:現金・貴重品運搬
-
4号業務:身辺警護(いわゆるボディーガード)
加えて、AI・顔認証・クラウド監視システムなどの先端技術との連携が進み、人間と機械の協調型警備体制が今後の標準となりつつある。
■ 結語
警備の歴史とは、「人を守る」ことに社会的責任を持った人々の記録である。
その根底にある理念と技術は、今なお現代の業務の根幹を成している。
我々は、この歴史に学び、今後も「安全」「安心」「秩序」の維持を、民間の立場から力強く支えていく所存である。
次回もぜひご覧ください。
![]()



